久々に麻雀の話。
前回、久々に麻雀をやった。
あまりアガれず、調子が悪かった。
昨日も麻雀をやった。
ラスだった。
ここのところ、麻雀の勉強を全くやっておらず、勉強したこともすっかり忘れていた。
前回はラスではなかったが、自分の中では前回の方が酷かった。
昨日は勉強したことを思い出せながら牌を切れたせいか、オリることを考えるようなレベルの配牌からアガることができたから、まだマシな方。
ところで、麻雀は運ゲーでもあるので、プロとか天鳳段位とか雀荘の常連とか高いレベルでもない限りは、勝ちたいという気合の強さがかなり影響しているように思える。
いわゆる”オカルト”の話になってしまうが。
メンバーに役もルールも用語もろくに覚えていない人がいるのだが、よくアガって、よくテンパイする。
その人=Kさんは昨日ずっと調子が悪く、ヤキトリかと思われた。
ところが終盤になって急にツキだし、大まくりで、序盤にアガりまくっていた先生を抜き去って2位に浮上して終わった。
どうしてよく分かっていない人があんなにアガれるのだろうと、いつも思う。
Kさんは入門者用の本しか読んでいない。
入門→初心者~中級者用の本を読んで勉強した私としては、正直面白くない🙃
Kさんの場合は切り方にセンスがあるのかもしれない。
だとしたら、センスは知能によるものだから、日本人の平均知能を下回る私は敵わなくなる。
明るい人なので運も呼び込むのだろうか。
昨日トップだったのは、10代のM。
初のトップだった。
Mはうちのグループに入ってきて暫くは元気がなかった。
元気がない間はずっと伸びなかった。
しかし、ここ半年くらいで随分と元気になってきたなと思っていたら、同時に麻雀も覚えてくるようになった。
ある時から急に「伸びたな」と感じるようになったのだ。
それからは会って卓を囲むごとに伸びていった。
そこは10代の若さなので、伸び出したら止まらない。
先生も「急に伸びた」と言っていた。
彼女は麻雀が大好きで、ネットでもオフでも打ち続けているので、これからも伸びるだろう。
やっぱり元気って大事。
Mが元気になって本当に良かった。
それにしても元気があるのとないのとでは、こうも吸収力に違いがあるのかと改めて考えさせられた。
うつ病だったころ、物覚えが極端に悪くなった過去の自分を思い出した。
さて、そうなると私が危機である。
今、私は他のことに気を取られているので、麻雀の勉強をしていない。
発達障害の特性ゆえに一つのことしかできない自分は、麻雀もやってアレもやってコレもやってという生活が難しい。
実は今の私が気を取られているのは、このブログである。
ブログを形作れれば、別のことに気が向くだろう。
その前は、WordPressで運営しているサイトの更新にかまけていた。
他にもやりたいこと、やらなければならないことはある。
麻雀は自分が何かを作り出す作業ではないので、私にとっては優先順位が低くなる。
それと、ADHDに加えて、私は頭の回転もめっぽう遅いので、ゲームの類は向いていないと、つくづく思わされている始末。
伸び出した10代には追い越されたら追いつけるはずもないし、センスがある人にも敵わないだろう。
麻雀をやることで、自分のできない部分ばかり自覚させられて、最近は劣等感しか湧かなくなってきた。
それだったら、他人と比較されることよりも独りで打ち込める作業の方が自分にとっては建設的ではないかとも思える。
こんな風に意欲が喪失した状態では、ますます他の意欲のある人たちに適わなくなることは明白だ。
中学生のころ、私はジャンケンが強かったのだが、気合が入っていたからだと思っている。
麻雀は運ゲーの要素があるので、気合は大事だ。
その上、グループの連絡役もまともに果たせなくなっている。
ただでさえADHDなのに、近年、更年期物忘れまで加わって、一層のこと頭が働かなくなってしまった。
ギフテッドではない発達障害者はどのように克服しているのだろうか。
しかし、かつてうつ病で何もできなかったころと比べれば、色々とやりたいことがあって自分を分裂させたいと思うくらいには回復できているのだから、幸せな悩みではないかと考え直すことにした。
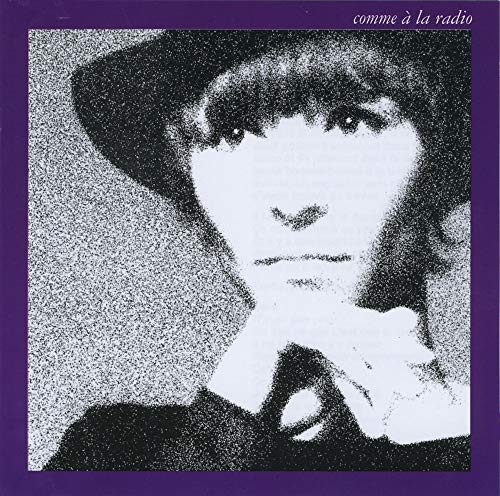
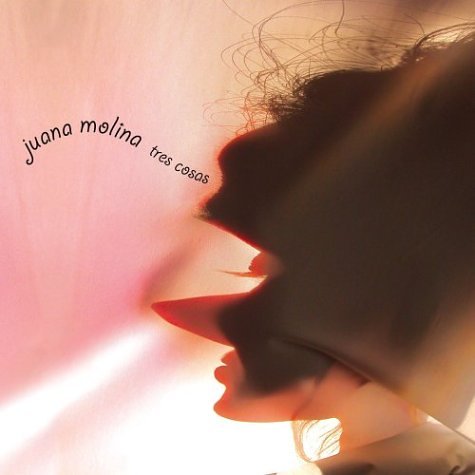

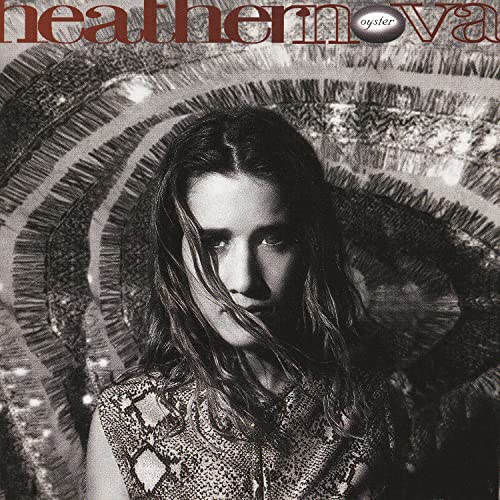


![Broken Politics [解説・歌詞対訳 / ボーナストラック収録 / 国内盤] (TRCP235) Broken Politics [解説・歌詞対訳 / ボーナストラック収録 / 国内盤] (TRCP235)](https://m.media-amazon.com/images/I/51ltT15SrVL._SL500_.jpg)








